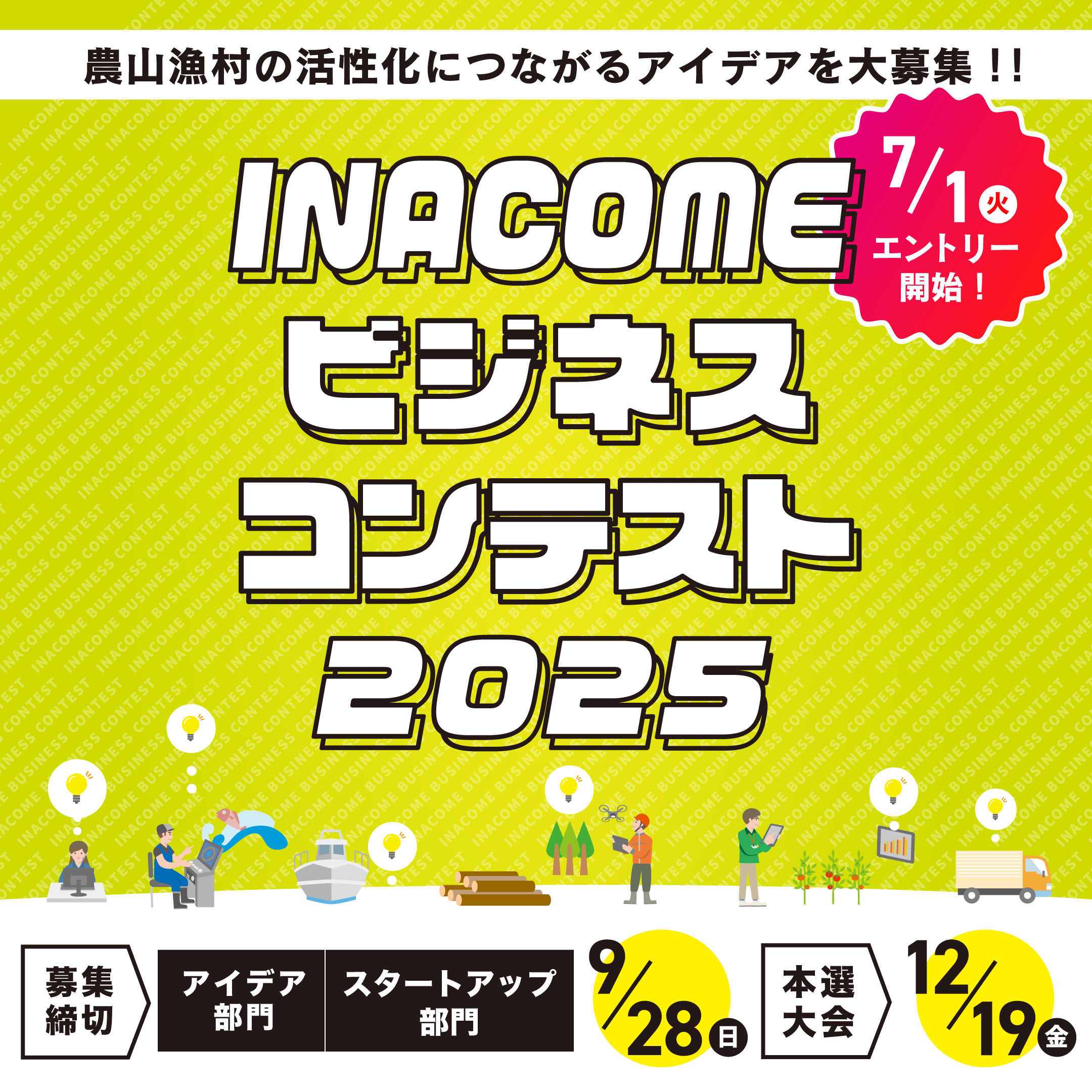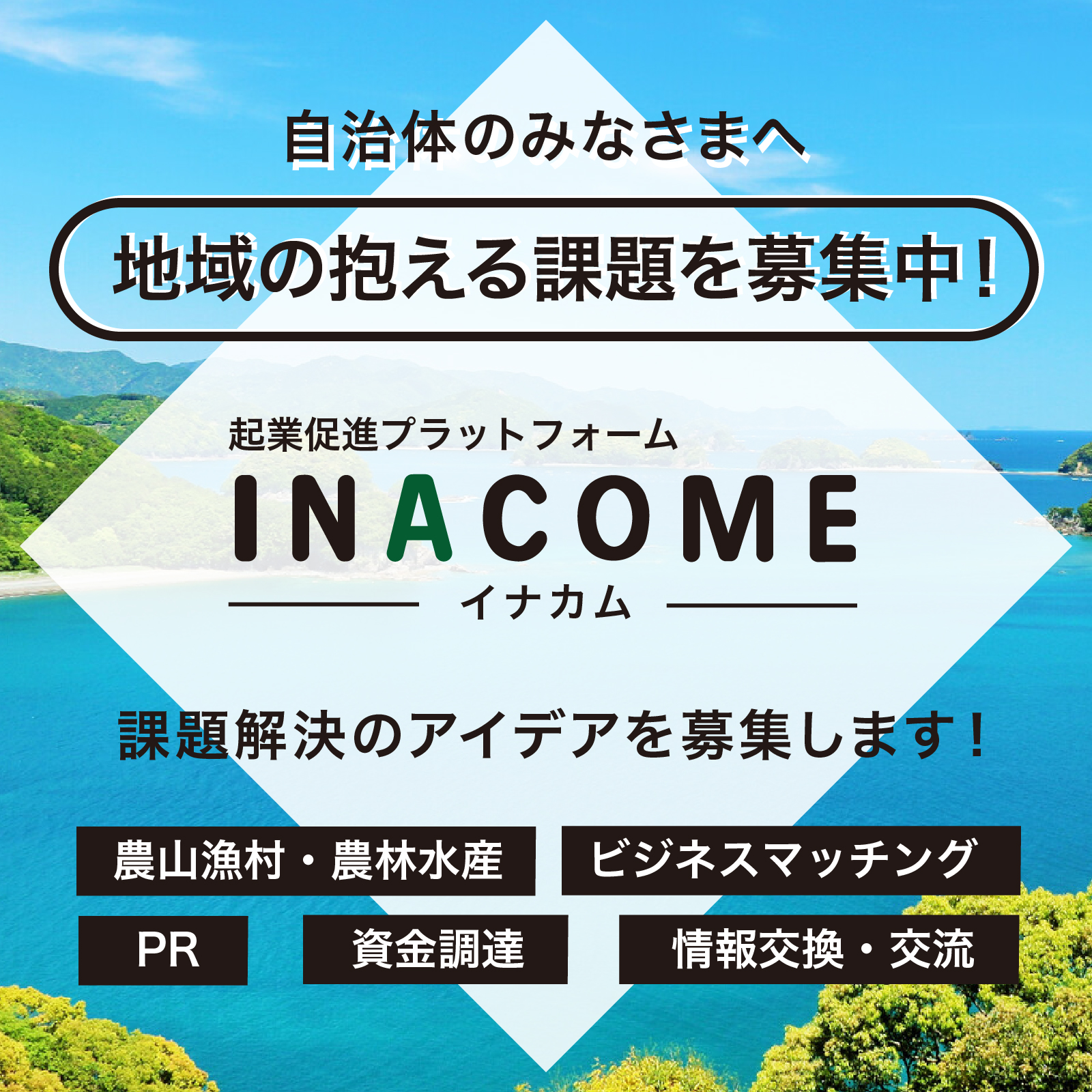-

-

-

-

-

-
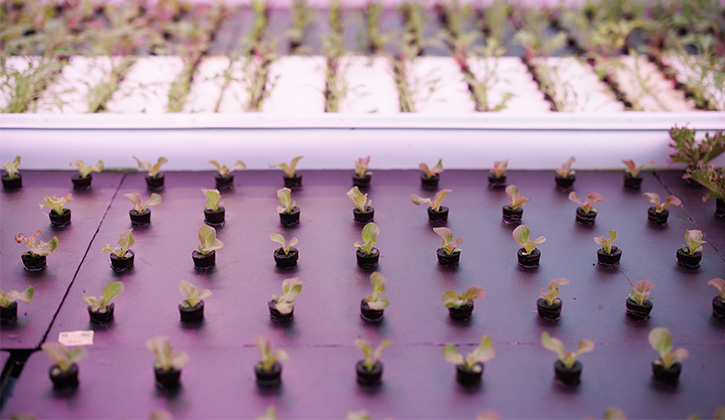
-

-

-

商売人人生50年の経験から大切にした「人と米」
栃木県コンクール優勝のブランド米を使ったお惣菜、地元農家が育てた朝どり野菜が買える直売所、耕作放棄地を活用して名物にまで成長したそばを使った手打ちそばレストランなどが愛され、中山間地にありながら年間1万人の来場者を誇る直売所とそばレストランの複合施設「いい里さかがわ館」。支配人の篠田隆さんは茂木町の道の駅で長らく店長を務め、定年を機に同じく茂木町にある地元・逆川へと戻り「いい里さかがわ館」の開業に従事。コミュニケーションを第一に周囲の人々を巻き込みながら軌道に乗せ、2008年の開業以来、一貫して右肩上がりの成長を続けている。

直売所「いい里さかがわ館」開業への道のり
開業前の逆川は活気を失っており、商店はわずか8件しかない状態。計画自体も町から疑心暗鬼の目を向けられていたという。しかし、そこは商売人人生50年の篠田さん。持ち前のコミュニケーション能力で難題を次々とクリアしていった。
「初期メンバーは8人。それじゃあいくらなんでも直売所は作れないと町に言われたのが最初のつまずきでした。すぐに同調者探しに奔走し、最終的には70人もの人々を集め、10万円ずつの出資を募り700万円を資本金にしてオープンにこぎ着けたんです」

従業員は地元登用。やる気に満ちあふれていたし、研修もしっかりこなして万全のオープン、のはずだったのだが…。
「接客などしたことがない素人の集まりでしたから、まず『いらっしゃいませ!』の声が出ないわけです。そして、そばの味が日によって変わるなど、それはもう大変な有様で。その状態からの脱却は難題で、人材の育成は開業から今日に至るまでで最も苦労したことじゃないでしょうか」
客商売というのは一朝一夕にはいかないもの。それは農業のプロたちにとってもそうであり、直売所で農作物を売ることが思いのほか難しいということに直面していく。まず農作物に偏り問題。例えば大根の時期には大根ばかりが並び、お客さんのニーズに応えることができないのだ。必然的に新たな品種への挑戦、多品種の栽培が必要で、お客さんとの対話を通した農業という経験のない取り組みが自然発生的にスタートしていく。そして、現在は名物となっている「美味しいお米が買える、食べられるさかがわ館」という確立も茨の道だった。