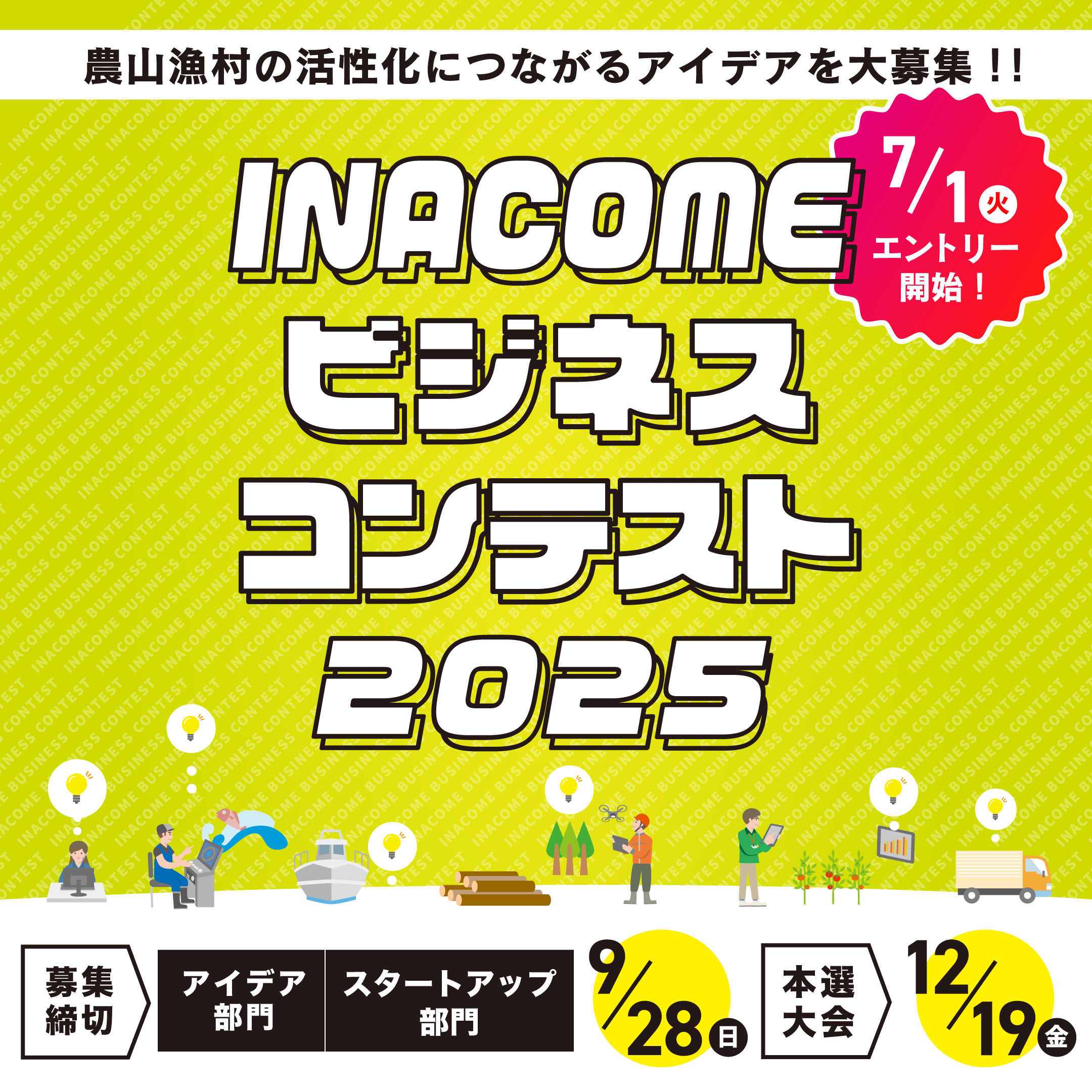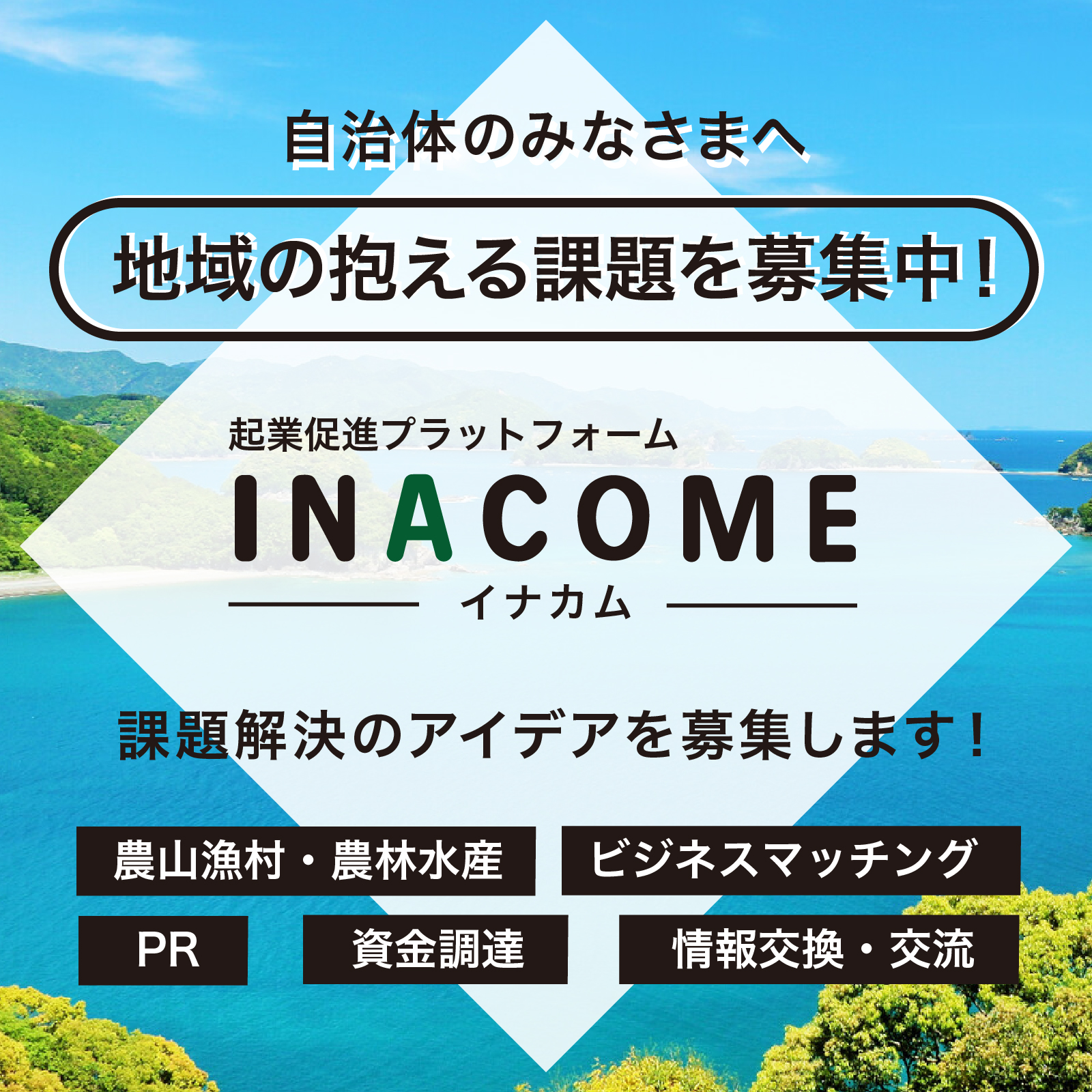-

-

-
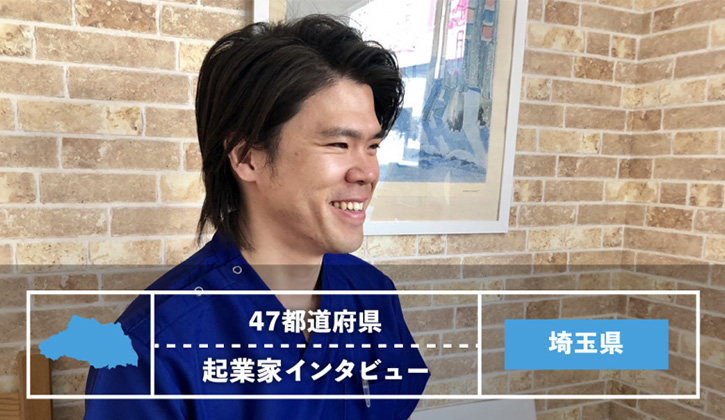
-

-

-

-

-

-

【宮城県で起業!】地方が抱えている課題は将来の日本全体の課題!NPOとして活動する理由

地域で活躍する多様な起業家を特集するこの企画。地方で起業することになった時、個人事業主か株式会社設立を考えるのが一般的です。しかし、中には特定非営利活動法人のNPOの形をとって地方起業に挑戦する人もいます。
「課題解決のビジョンに共感した人・組織を巻き込み、動きやすいのはNPO」と語るのは、NPOアスヘノキボウ代表 小松洋介さん。今回は、株式会社ではなくNPOとして活動するメリット・デメリットや行政と協力関係を結ぶ上で大切な心構え、都会ではなく地方で起業する醍醐味について詳しくお伺いしました。
地方で抱えている課題は、将来の日本の課題だと思う。

女川町の復興した商店街シーバルピア女川
ーまずはじめに、小松さんが代表を務められている団体について教えていただけますか。
小松)小松洋介と言います。宮城県女川町を拠点に、NPOである特定非営利活動法人アスヘノキボウの代表をしています。女川町は2011年の東日本大震災で7割を失ってしまった町で、地震以後、アスヘノキボウは復興のまちづくりから女川町に携わり、今に到るまで活動を続けています。
ー大震災以降、復興や街づくりなどを進める中で、なぜ女川町を拠点にNPOを始められたんでしょうか。
前職の新卒時代に営業で飛び込んでいたエリアが宮城県三陸沿岸部で、飛び込む先々のクライアントの方々に可愛がってもらい、自分の中では何かあれば戻り、原点に立ち返る場所になっていました。自分の場合は、もともと起業したいと思う気持ちが非常に強かったので、会社を辞めて独立起業も考えていた矢先に大震災が起こりました。
愛着のある三陸沿岸部の町々が津波に飲まれたことがショックで、何かできることと考えて週末、宮城に戻りボランティアを始めました。ボランティアを通して、会社のOBの先輩と一緒に東北被災地を回っている中で、地方の課題を目の当たりにしました。そんな時に、女川町の商工会の方に声をかけていただき、女川町の復興まちづくりに関わることになりました。
ー被災地を回っている中で、地方の課題を目の当たりにされたとおっしゃっていますが、具体的にはどんな課題なのでしょうか。
地方で抱えている課題は、日本の将来の課題だと思っています。人口減少、少子高齢化、労働力不足、医療福祉の問題など地方で問題になっていることは近い将来、日本全体の課題になっていきます。被災地では震災により、この深刻な課題がより加速し、日本の課題先進地になってしまったと思ったのです。僕たちは、アスヘノキボウで活動し、女川町の社会課題を解決しながら、日本の社会課題を解決していくことを大切にしています。
VENTURE FOR JAPANを通じて、地方でキャリアを積んだ日本を代表する起業家を増やしたい。

VENTURE FOR JAPANの説明会の様子
ー先ほど、地方の課題は日本の将来の課題だとおっしゃっていました。アスヘノキボウでは具体的にどのようなことに取り組まれているんでしょうか。
大きく2つに分かれます。1つ目は女川町と公民提携して進めているものです。まずは、「女川健康プロジェクト」。女川の課題として1人あたりの医療費が増えている点が挙げられます。そこで、アスヘノキボウ、女川町、ロート製薬さんと組んで「10分無料カラダチェック」やチーム対抗で行われる「健康100日プロジェクト」、企業ごとに健康経営のアドバイスなどを実施してきました。
他には、町内外にかかわらず町で活動する人を増やす「活動人口創出促進事業」も行なっています。女川町に5〜30日間の無料で試しに住んでみて、女川・地方との関わりを考えたり、深めたりする「お試し移住プログラム」や女川町に限らず日本中の地方で起業しようと考えている人すべてをサポートする豪華講師陣が集まった「創業本気プログラム」などをやっています。お試し移住は年間100名以上(うち80%が大学生)が参加、創業本気プログラムは参加者の7割が起業・起業準備に入っています。
2つ目が自分たちで単独で行っている事業です。それが、VENTURE FOR JAPANです。こちらの事業の対象は、女川町だけでなく、日本全国へ広げていく事業になっています。一言で事業をまとめるならば、「経営の実践を新卒・第二新卒から経験して、日本を代表する起業家をつくる事業」です。
ーこちらは女川町を拠点にしてはいないんですね。始めるきっかけは何だったんでしょうか。
事業を始めるきっかけは女川町が被災地となり、学生のボランティアやインターンが増えたことでした。 彼らは、東北で活動し、「将来起業したい」「社会をよくしたい」「自分の力で食える人間になりたい」などの気持ちがあるにも関わらず、大学卒業が近づくと就活というものに思考停止してしまい、「とりあえず勉強のため」、「社会を知るため」などという理由で大企業就職を選択をする人が多いんです。 これを僕は社会問題だと思っています。ですが、その根源を調べていくと、大学卒業時に進学以外の進路を考えると就職活動(大企業がよしとする就職活動)以外の選択肢がないんです。
だからこそ、新卒学生・第二新卒などの若者で「将来起業したい」、「自分の力で食えるようになりたい」という挑戦したい子が挑戦できる進路をつくりたいと思いました。ベンチャーフォージャパンでは、起業家を目指す主に新卒・第二新卒を伸び盛りの地方の経営ポストに2年間送り、経営者の右腕ポジションで経営の仕事してもらいます。若者の参加者からすれば、実践的に経営を学べますし、逆に経営者からすれば右腕人材がつくことで、既存事業の拡大、新規事業開発に取り組む余裕も出てきます。
ベンチャーフォージャパンに参加する若者が増えれば、震災ボランティアやインターンをして就職の選択肢だけではなく、地方で経営を学ぶ修行し、将来起業する選択肢も出てきます。そうなると、女川町だけでなく、日本の地方から若者の力で社会課題解決や日本をよりよくする事業がたくさん立ち上がってくるのではないでしょうか。
多くのセクター・組織と組め、動きやすいのはNPO。

小松さんとアスヘノキボウのスタッフのみなさん
ー小松さんの活動についてここまで聞かせていただきましたが、なぜアスヘノキボウは株式会社ではなく、NPOとして活動されているんでしょうか。地方起業だとNPOの方がいいのでしょうか?
株式会社ではなく、NPOにしたのにはもちろん理由があります。地域の社会課題を解決する上で多くのリソースが必要になります。そのような時にNPOだと純粋に社会よりよくすることをテーマに多くのリソースを集めることができます。また、複数のセクターをまたぎやすいのも特徴です。
ー複数の異なる組織と組みやすいんですね。でも、それは株式会社でも同じではないのでしょうか。
基本は同じだと思います。しかし、例えば、NPOで事業を行なった場合は、社会課題解決に向けて純粋に問題定義ができ、利害関係もなく、自由に必要なセクター・組織と組めるので話はしやすいですね。また行政側の視点になると、株式会社に仕事の依頼することになると、「なぜこの会社なの?」という問いが生まれることがあります。
行政からすると、全民間事業者に対して平等性が問われますからね。そのため、社会課題に向き合うには、NPOのように「社会課題解決」を大名目における方が、いろんな人と組みやすいんです。特定非営利活動団体ですし、株式会社と違って利益のみを求め続けるわけではないからです。行政・民間企業からしても、NPOは組みやすい部分が多いと思うのです。ただ、自分たちはNPOとしてスタートした6年前よりも株式会社でもまちづくりはできるようになったと感じていますし、株式会社やるのも1つの選択肢だとは思っています。
地域のことを徹底的に知ることで、協力体制を築くことができる。

女川健康プロジェクトにあたり、行政とロート製薬さんとの協定調印式の様子
ー小松さんのお話を聞いていると、行政と良好な関係を築けている印象を受けました。地方の方々と意思疎通が取れない、話が噛み合わないの声も聞きますが、何か心がけているポイントはありますか?
まずは、町のことを徹底的に知っておくことですかね。女川町の場合は、行政や議会、商工会、産業界、市民団体など、どのような組織があり、日々どのような議論が行われているのかを理解するようにしました。まずは、そこを理解してないと協力体制も築きづらいですし、うまくいかないと思います。これは、移住もそうですし、地元で起業する場合もですね。地元であろうと地元でなかろうと、時間かけてでも深く地域を知っていくことは不可欠だと思ってる。
ーどのように地域を知って行けば良いのでしょうか。
基本的には、町の広報・議会だより・町の総合戦略・地域のある組織のウェブなどを読み込むこと、間を歩いてのヒアリングですね。今は広報や議会だより、総合戦略もウェブで見られる時代ですし、どこでも調べることができます。ヒアリングは自分の短な方にヒアリングして、何か面白そうな話が出てきたら関わる人を紹介してもらい、他の人に聞いてみたり。町のそれぞれの団体さんが、どのような動きをしているのかなどを丁寧に知る必要があります。
繰り返しになりますが、地域のことを徹底的に知ることは地方で活動するにあたって必ずやらなくてはいけないのではないかなと思いますね。先ほどの行政とNPOの提携じゃないですが、行政のルールや思想を理解するのは必須です。
これから地方で起業する人には、都会と地方の醍醐味を感じて欲しい。

ー最後にこれから地方で起業したい人やNPOを立ち上げて活動していきたい人に向けて一言お願いします。
せっかく地方で起業するからには、地方で起業する醍醐味を感じて欲しいです。地方は、地域の行政、議会、産業界、住民の距離が非常に近いです。考えてみてください、東京で起業しても行政職員や議員さんに会うことはほぼないですよね。都庁に行くことはほぼありません。一方で、地方にいけば地方の行政の職員の皆さんはもちろん、議員さんとも会えますし産業界の社長さんにも住民の方にも会うことができます。ただ会って終わりではありません。彼らのような様々なセクターを巻き込んだ事業を仕掛けることができます。地域全体をを巻き込んで起業することが何よりも醍醐味です。
地方でやるから規模もインパクトも小さくしかできないなどと思うのではなく、「地方から日本社会を変える。地域を巻き込んで面白い事業を作る」くらいの考え方でいると良いと思います。都会で起業したら、あまり地域を巻き込むことがないので、自分たちで勝負することが多いように感じます。地方の場合は、巻き込んだみんなが気にかけてくれます。人と人が繋がって事業ができるし、事業立ち上がった後もサポート・フォローしてくれる人がたくさんいるのは、面白みがあるし、何より人の温かさを感じてありがたいですね。
最後に、この記事を読んでいる大学生に一言。VENTURE FOR JAPANは、私たちが自信を持って生み出したプログラムなので、ぜひ申し込んでくれると嬉しいです。これまで話したような面白い地方で修行して、将来起業し、新しい社会のうねりを共に感じましょう!
 Twitter
Twitter