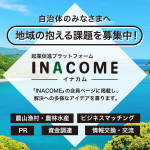-

-

-
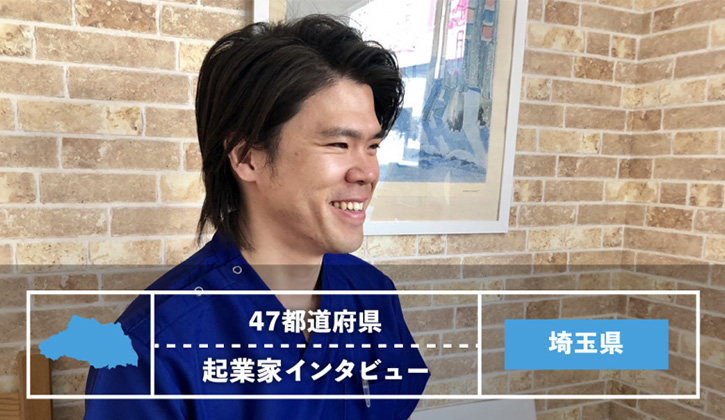
-

-

-

-

-

-

【岩手県で起業!】”リノベーションまちづくり”を通してチャレンジする大人が集まる街をつくりたい!
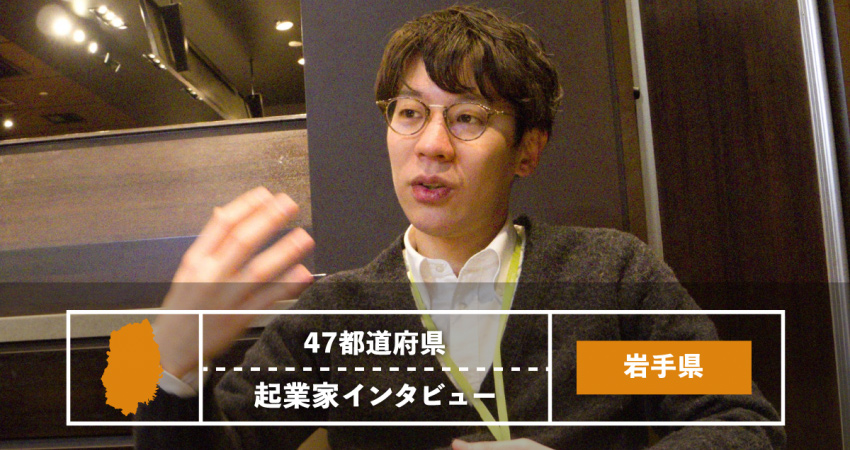
地域で活躍する多様な起業家を特集するこの企画。6つの企業の経営をしながら、地元である岩手県花巻市で、まちづくりの先陣を切り開いてるのが、花巻家守舎代表・小友康広さんです。次々と新たな事業を成功に導く手腕、考え方について、お話を伺いました。
―小友さんは大学卒業後、一度就職されたんですよね。
小友)実家の木材屋を継ぐ前に、どこかの会社で修行しようと思ったんです。いろいろ会社を見たなかで、一番良いと思ったのがスターティアでした。当時は50人ほどの会社で、名前もお金もなかったけど、情熱がある人たちが集まっている会社でした。ここを大きくする経験をすることが自分にとってプラスになるんじゃないかと思い、就職を決めました。新卒4年目の時には、分社化してスターティアラボという新会社を作る経験もしました。
―花巻に関わるようになったきっかけはあるのでしょうか?
27歳の頃、父にがんが見つかったタイミングで、家業である小友木材店の専務になりました。仕事を覚えるために、月のうちに3、4日ほど花巻に帰るという生活でした。父は一旦手術して大丈夫になったんですが、数年後には全身転移が見つかり、僕が30歳の時に亡くなりました。それで僕が小友木材店の代表になりました。
―それから、新たに起業した家守会社のような事業にも繋がったんでしょうか?
それは完全に偶然なんです。木材屋さんあるあるなんですが、木材業がいい時は、物流もいい好立地に工場などを持っていて、木材業が衰退していくと不動産業にコンバートしていくんです。その中でも駅前にあった自社ビルが、築50何年のボロボロで、テナントが全然つかないのをずっと見ていました。父が亡くなった時に、解体して駐車場にでもしようかと思い、見積りを取ったら2千数百万円がかかることが分かりました。駐車場にしても3万円しか儲からないので、50年回収。なかなか手が付けられない悩みを持ちながら、一旦放置していました。
そうした時、花巻市から勉強会の誘いが電話で来たんです。オガール紫波を立ち上げた岡崎さんが「家守勉強会をやります」と。たまたま時間も空いていたし、当時オガールは全国から注目されていたので、その経営者の話だったら面白そうだな、と思って行きました。そこで初めて、リノベーションまちづくりや、家守という手法を知ったんです。その話に感化されて「うちのビル単体で考えれば限界があるけど、この方法で、エリア全体で考えたなかの起点になれたらすごくいいんじゃないか」と思い、その場にいた2人と僕、市役所職員を集めた4人で花巻家守舎を起業しました。

―地域の中で集中的にリノベーションをすることでエリアの価値を上げていく「リノベーションまちづくり」のモデルは、今全国でも広がっていますね。花巻家守舎を立ち上げるにあたり、他の創業メンバーの方はどんな思いを抱えていたのでしょうか?
取締役の高橋潤吉さんは、地元の建設会社で働きながら、商工会青年部の副会長として花巻をどうしていくといいのか考えていた時に、リノベーションまちづくりを知りました。自分の仕事と関わりながら出来るということでやる気になりました。もう一人取締役の高橋久美子さんは、オーガニックカフェ兼ヨガスタジオをやろうと思っていましたが、条件に合う物件がなく、どうしようか考えていました。市役所職員の伊藤直樹さんは、都市政策で補助金をバンバン出していたなか、補助金に意味があるのか悩んでいました。だからそれぞれやりたいことと、家守会社のやることをマッチングさせられていたことが良かったです。
―今も4名は自分の仕事をしながら家守会社をやっているのでしょうか?
そうです。リノベーションまちづくりの提唱者の清水さんからも、家守会社は副業でやりなさいと言われていました。最初は儲からないですし、ずっと忙しい業態ではないので。本業で儲けられていて、余力をまちに投資する状態が合っています。まちの未来で儲けようと思うと、ひずみが出てしまいます。リノベーションまちづくりは、利益が少しずつ増えていくことが継続していきながら、何十年と続いていく超ストック型ビジネスなので。
それに、経営力は売り上げを最大化することだと思われていますが、利益を最大化することです。だから、今の仕事をやめなきゃいけないという概念に囚われると難しいと思います。「今の仕事をやりながら、土日の範囲だけでどうしたら儲けられるようになるだろう」、「月一で収支を合わせていくにはどうしたらいいだろう」。そういう考え方ができない人は多いですが、本当は両方取れる。そういうやり方がいいと僕は思います。
―地方と東京の二拠点で働いている小友さんに伺いたいのですが、外から見てみて、地方で起業することのメリットはどのようにお考えですか?
僕にとっては地方ではなく、地元なんです。もし僕が、例えば他の地方でいきなり起業したとしたら、こんな働き方が出来ているとは思えません。祖父の代から花巻に住んでいて、「三代住めば江戸っ子」で言うなら、僕が三代目で土着ですから。
2年前マルカンビルのリノベーションをやると決まったときに、70代の従業員の再雇用のために面談をしたんです。そしたら「実は、旦那が小友木材店さんにお世話になったことがありまして」とか「おじいさんには大変お世話になりまして」という人たちがいました。また、父の同級生が「君のお父さんは早く亡くなっているから、俺たちが親父代わりだと思って止めに来た。そんな危ない橋を君に渡らせるわけにはいかない!」と言ってくれることもありました。応援するのも心配するのも、僕だけでなく小友家として見ているんです。だからみんな、家族として支援しようとしてくれます。
それは農村社会の良いところだと思います。「異分子っぽいけど、根っこは花巻人だ」という見方をしてもらっているんです。なので、はじめから信用や信頼が高い状態からスタートできます。よく「恩送り」って言いますよね。農村社会では誰かに恩を貸す時に、自分でなく次の世代に返ってくる考え方が前提にあるんだと思います。僕にとっては、父や祖父がいてくれたことがすごく大きいです。
―3年前に一度閉店したマルカンビルは、花巻市民全員の食堂であるかのように親しまれていたとお聞きしました。大規模なビルのリノベーションに踏み切った理由を教えてください。
大食堂がなくなるのが嫌だったから。それだけです。僕が食べたいマルカンラーメンは味だけでなく、雰囲気までセットだったんです。そして友達に自慢したかったんですよ。「花巻にはこんなところがあるんだぜ」って。「地域がよくなる」ということが、僕はあまりよく分からないんです。それよりも、僕が欲しい暮らしができるか、僕が友達に「俺の地元はどうだ、いいだろう。大好きなんだよね」と言える、誇らしい街であることが第一です。
あともう一つ、僕の好きな人がいるかが大切です。そして、僕が好きなのはチャレンジしている人。自分の理想と現状とのギャップを見たときに、少しでも自分の力で理想に向かって何かを作っていこうとする人が大好きなんです。誰かにやってもらおうというような人は何万人いても変わらないと思ってしまいます。それより100人でも、自分で覚悟を持って、お金と時間を投資して実行する人がいることが大切です。僕が欲しい人、好きな人がどれだけこのエリアにいるかが、僕にとってすごく価値なんです。

―大きな主語で一括りに捉えるのではなく、自分のリアルな経験を通して、まちを考えているんですね。これから将来の展望というよりは、自分の中でやりたいことを実行に移していくということなのでしょうか?
個人としてはそうです。個人としては、わくわくするかと、今の自分よりも成長の機会が存在するかで、次にやることが決まります。 ですが、会社ごとにビジョンがあります。花巻家守舎は「チャレンジする大人が集まる街をつくる」。何か挑もうという時にみんなから応援されるまちにしようと、花巻駅前で活動しています。そして、上町家守舎は「花巻の産業が育つ街にする」。僕の友達しかり、観光客しかり、来た時に上町にいれば花巻の良いところが全部味わえる、ハブ的な役割です。
上町は、花巻に来た人たちが飛行機で来ても、新幹線で来ても、在来線で来ても、おそらく一度は必ず通る場所です。だから、そこを上町、花巻に波及させていくことがビジョンです。それには、僕らが全てやるのではなく、これに共感する人をどう集めるかが大切です。ただ、おかげさまで僕らとは関係なくやり始めている人たちも増えています。「駅前にブリュワリーを作るんだ!」って言って700万円をかけている人もいますし、「ネイルサロン独立して始めたいから、物件を探してほしい」など、僕のところに相談が来て紹介したことも4、5件あります。事業として絡んだものもある、まったく事業として絡まなかったものもあります。
―小友さんはご自身で起業した花巻家守舎、上町家守舎のほか、複数の企業を経営をしていますよね。その中で意識していることはありますか?
全部は自分で出来ないので、任せることです。その時、権限と責任をセットで渡すことはすごく意識しています。例えば、月に100万円まで自由に決済していい権限を渡したとしたら、もしその100万円の使い方が上手くなかったとしても、途中でひっくり返すことはしないようにしています。それは僕が100万円の決裁権限を与えたのがまずかったという話なので。だから次からは50万円までなど、基本的にはその次の行動を制限するしかないと思っています。
あと、僕の考え方を可能な限り開示するようにしています。Googleの統計調査では、Google社内ですごくパフォーマンスを出している上司の行動特性は「次の行動が読めること」だったそうです。上司の頭の中が見える化されていないと、部下の行動は小さくまとまってしまいます。僕が、何が好きで何に喜ぶか、何が嫌っているかということを分かりやすいようにしています。
―今の働き方が小友さんにも合っていたんでしょうか。最後に小友さんのスタイルを教えてください。
合っていたというより、合わせていったんだと思います。僕はこだわりがないんです。やりたいことは世界で一番かっこいい木材屋を作ることだけで、それ以外は人のビジョンに乗っかるのも全然悪くないと思っています。よく“アドリバー”と言っているんです。僕はずっと音楽をやっていて、ジャムセッションやアドリブが好きなんです。型だけが決まっていて、全然知らない人とセッションするように、面白そうな案件が来たときに、わくわくして今の自分の実力が足りないものなら掴んでしまう。すべては、そこから考え始めます。
 Twitter
Twitter